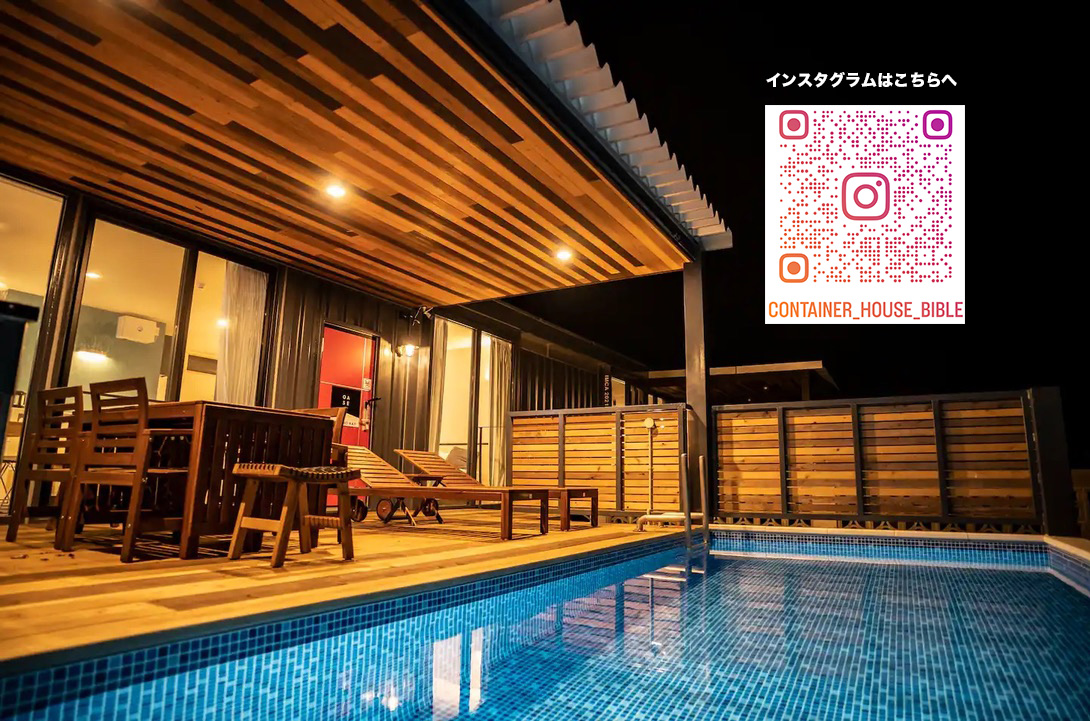アフターコロナの時代に要求される「コワーキングスペースの標準設計」=郊外の住宅街に出現する「コワーキングスペース」
自由な仕事の取り組み方とそれを可能にする空間企画(創造の杜企画)
新コロナウィルス の渦中の時でも「コワーキングスペース」が盛況で、少々困惑した感じになっていました。当時避けようとしていた3密になってしまうからです。なぜ、コワーキングスペースに人々は押しかけたのでしょう。
私は、コロナ渦がひと段落すると、アフターコロナの世界では「コワーキングスペースのニーズ」に新たな変化が生まれると考えています。都心型ではなく、郊外型のコワーキングスペースのニーズが高まると考えています。今まで見向きもしてくれなかった「住宅街の駅そばに俄然このニーズが高まる」と考えています。
その理由は「Tele_work」がアフターコロナの世界では、定着するからです。「Tele_work」の有用性は兼ねてから語られていた事ですが、「働き方改革」の後押しも虚しく、理解しない会社の上司たちは改革的変化を望みませんので、それを広げる、あるいは定着させる事をしませんでした。しかしコロナ渦の時には、必要に迫られて多くの企業が導入しました。その有用性を多くの人々が確認することになりました。
この事は、コロナ渦が終わってもその企業の多くがそのまま導入し続ける割合が高いと考えるのが必然でしょう。企業にとっても固定的な経費の節減になります。コミュニケーションに問題がない職種では、「通勤者の数を減らす努力」に合致します。
また、それに加えて都市構造も変化をし始めます。昼間人口の多い都市部から人が減少し、住宅地の昼人口が増加します。都市部に流れる人の数が減少するからです。この仕事の仕方は、本当は、かねてより皆も望んでいる事でした。しかしながら、急に取り組んだコロナ渦時の「tele_work」の状況では望まない状況があります。
それは「家でやりたくない」という切実な願いです。「狭い」「うるさい嫁がいる」、「可愛いけど、遊べとうるさい子供がいる」、幸せなはずの構図は仕事の上では必ずしもそうでもありません。世の中の方々はそう考えます。それだけではなく、「仕事のオンオフにメリハリつけたい!」そう考えます。
郊外住宅街駅そばのスペースに「コワーキングスペース」があると、通勤するでもなく、近隣のコワーキングスペースで仕事に専念する事が出来ます。このニーズが俄然高まるのです。今までは「コワーキングスペース」はどちらかというと「都市部」でした。それはそれで今まで通りニーズはあるのですが、爆発的に増えるのが「郊外型コワーキングスペース」なのです。今までのコワーキングスペースは「小さな会社」や「フリーランサー」の方々にとって便利なオフィススペースでした。これからは「仕事をtele_workで行う」方々にも歓迎される空間となるのです。
この取り組み方が「普通」になって行く背景の中で、「レンタルオフィス的概念」にも変化が訪れます。それは「WE WORK」などの活動の中でもコワーキングオフィスが孤独な小事務所の集合体ではなく、「自由な発想の新たな時代の仕事のやり方」というイメージが定着し始めていたものが、加速的にその概念定着が行われ、時代的に「普通のあり方」あるいは「先進的なあり方」に変化していくのです。
コワーキングは独立して働きつつも価値観を共有する参加者同士のグループ内で社交や懇親が図れる働き方でもありますから、コスト削減や利便性といったメリットだけではなく、才能ある他の分野の人たちと刺激し合い、仕事上での相乗効果が期待できるという面も持っています。さて、そうなりますと運営側へのホスピタリティの高さも要求されるようになって行くのは間違い無いですが、それは「コスト」と共にあるものですから、開発する「新業態」の位置付けをはっきりすれば良いだけです。ただし、「ここまでは装備しよう」という新たな指標は出来て来るのでしょう。
それらを総合的に考えた企画をお届けいたします。

この展開の方向にはいくつかの方向性があると考えています
●徹底的に個室型のニーズを追求する形
●徹底的にシェアオフィス型の床効率重視型の「協業スペース」を重視する方向
●その中庸の方向性=(個室と協業スペースの両方をバランスよく取り入れる方向)
アフターコロナ渦の「tele_work」スペース確保を一つのコンセプトとした時
まさに「tele_work」の仕事のやり方の一つのシーンである「NET_会議」対応の必要性があります。
この対応には「話声対策」が絡むので「個室型」のニーズが多い事が予想されます。
あるいは法人登記「NET_会議」用スペースをオプション等で準備するなどの対策が考えられます。
一方で普通に「喜んで頂ける快適なオフィス空間」である事が重要です。
まずはアフターコロナのオフィスとしての「新時代生活様式のクリア」=「環境衛生概念の徹底追求」
また、オフィスとしての要望は概ね2つの方向性が考えられます。�一つは単純にオフィス機能のサービスです。

1.複合機などの機能サービス(PDF、コピー、FAX(?いるかな)
2.電話秘書サービス
3.宅配便や郵送物の代理送付、代理受け取りサービス
4.起業のための「法人としての登記可能サービス」
5.打ち合わせスペースの確保・会議室の確保
などです。
もう一つは「ホスピタリティ」
1.フリードリンクサービス
2.OFF感覚の休息スペース�3.フリースペース用の「電話ブース」
建築空間として「新時代生活様式のクリア」=「環境衛生概念の徹底追求」も行わなければなりません。
十分な容量の「換気設備」、空気の流れを熟慮した空気調和設備、衛生概念を十分取り込んだトイレ設備などです。
この企画において必要と考えられる機能空間および設備を列挙します。
A1.個室的執務スペース
A2.協業用執務スペース
A3.会議室・打ち合わせ室(NET会議可能な設備付_又は高速WiFi)
A4.休息スペース
A5.運営側事務スペース
A6.講習会などを開催できるスペース
A7.休息スペース又はCAFEのようなスペース
A8.トイレスペース
A9.郵便・宅配受け取り装置
B1.除菌機能付きエアコン(次亜塩素酸による殺菌)
B2.共用空間の扉などは「自動扉」(触らずに済むもの)
B3.個室の空気調和設備は「外気導入型陽圧系」とする(他の共用空間などから空気の流入がない)
B4.一般的感染防止策の徹底
B5.トイレなどの「除菌」グッズの徹底
B6.WEB会議が無理なく可能なデジタルインフラ(高速インターネット導入)