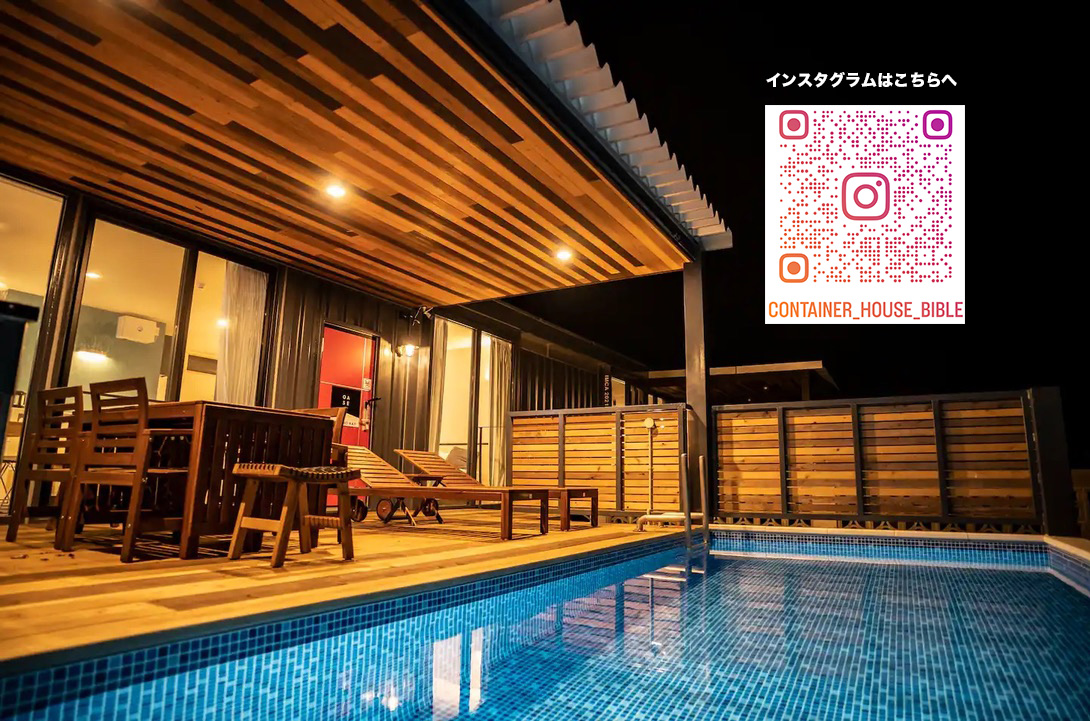なぜ人は“コンテナでを建てたい”と思うのか?四半世紀以上コンテナ建築をやってきて、そして今「コンテナハウスの歴史」という本を書いていて、ようやくわかった。
話をわかりやすくすると「ロック」と「レゴブロック」の間にある建築衝動について語ればいいということもわかってきた。
無骨な鉄の箱に、なぜか惹かれる
いつも、面白い相談が舞い込む。それを仕事としていますが
「コンテナで家を建てたいんです。」
「お店をコンテナでやってみたい。」
しかもこれは都市部だけではない。北海道から九州、離島まで、各地に“その気のある人”が一定数存在している。
彼らに共通するのは、合理性よりも“感覚”を先に口にすることだ。
「なんか、あの感じがいいんですよ。あの、無機質な……」それはきっと、港に積まれたコンテナの風景が、どこか“反骨”や“孤立”といった言葉を連想させるからだろう。
誰とも違う、自分だけの空間を持ちたい。そんな欲望が、あの鉄の箱に投影されている。彼らは皆、どこか「自分の拠点」を求めているのだ。
そこには「ロック」の匂いがする。流行でも制度でもなく、“好きだからやる”。鉄の塊に暮らしを持ち込む。それはちょっと乱暴で、不器用で、でも確かに“かっこいい”。

制度ではなく、「世界観」をつくるために建てる。とはいえ、現実は甘くない。日本の建築制度では、コンテナはそのままでは「家」にはできない。建築基準法第37条に定められた「材料規定」により、構造材としての品質や性能が求められ、海外製のISOコンテナがそのまま使えるケースはない。

断熱、構造補強、基礎工事、そして行政との協議。ありとあらゆるハードルを超えて、ようやく“建築”として成立するのが、コンテナハウスである。でも、それでも人はやるのだ。制度的に苦労があることを知っていても、「それでもやりたい」と思ってしまう。
それはなぜか?その理由は、“合理性”では説明できない。「建てる」という行為を通して、自分の“世界観”を表現したいのだ。むしろ建てたあとの住まい方、暮らし方までを含めて「ひとつの表現」なのだ。
コンテナの中にアナログレコードを持ち込み、アイアンの什器を置き、裸電球をぶら下げて暮らす。それは自己演出ではなく、自己信念の環境化だ。つまり「自分の物語に合った舞台を、現実世界に作る」行為なのだ。
レゴブロックとロックンロール
コンテナハウスという言葉の中には、「レゴ」と「ロック」が同居している。レゴは言うまでもなく、組み立てる楽しさと論理性の象徴だ。モジュールを並べて、積んで、組み替える。合理的でありながら、無限の創造性を持つ。

一方のロックは、衝動的で、反体制的で、直感的。社会の枠組みを少し斜めから見ている。コンテナ建築には、この両者が奇跡的なバランスで同居している。決められたサイズ、決められた角。世界中の物流と互換性のある“完全な規格品”でありながら、
その中に「自分だけの不完全な生き方」をぶち込むことができる。
それはまさに、「JIS規格にロック魂をねじ込む」行為なのだ。現代建築で、これほど両極を併せ持ったものは、なかなかない。しかも、それが“家になる”という感動は大きい。ブロックのように積んで、自分で運んで、自分で改造できる。家というより「基地」に近い。誰かの評価や不動産価値ではなく、自分の物語をそこに宿らせる。
コンテナハウスは、いわば“生き方のプロトタイプ”でもある。
「建てたい」のではなく、「生きたい」のだこう考えると、やっぱり結論はこうなる。人は、コンテナで“建てたい”のではない。
コンテナで“生きたい”のだ。その人の生き方や表現したい世界観が、コンテナというモノに託されている。デザイン性や構造技術の話ではなく、自分の思想を“鉄の箱”に封入して、世界に向けて存在を表明する。

それは、設計図というより、ライフスタイルのマニフェストだ。私たちIMCA(現代コンテナ建築研究所)は、そんな想いを「建築」というかたちに翻訳する技術集団でありたいと思っている。それは、図面を引くことでも、構造計算をすることでもなく、「その人の生き方の容れ物を共に考える」ことに他ならない。だから、また誰かが口にする。
「なんか、いいんですよね。あの感じが。」それで、いいのだ。その“あの感じ”の正体こそが、きっとロックであり、レゴであり、あなた自身の旅の始まりなのだから。
ということに気がついた。四半世もかかりましたけどね。