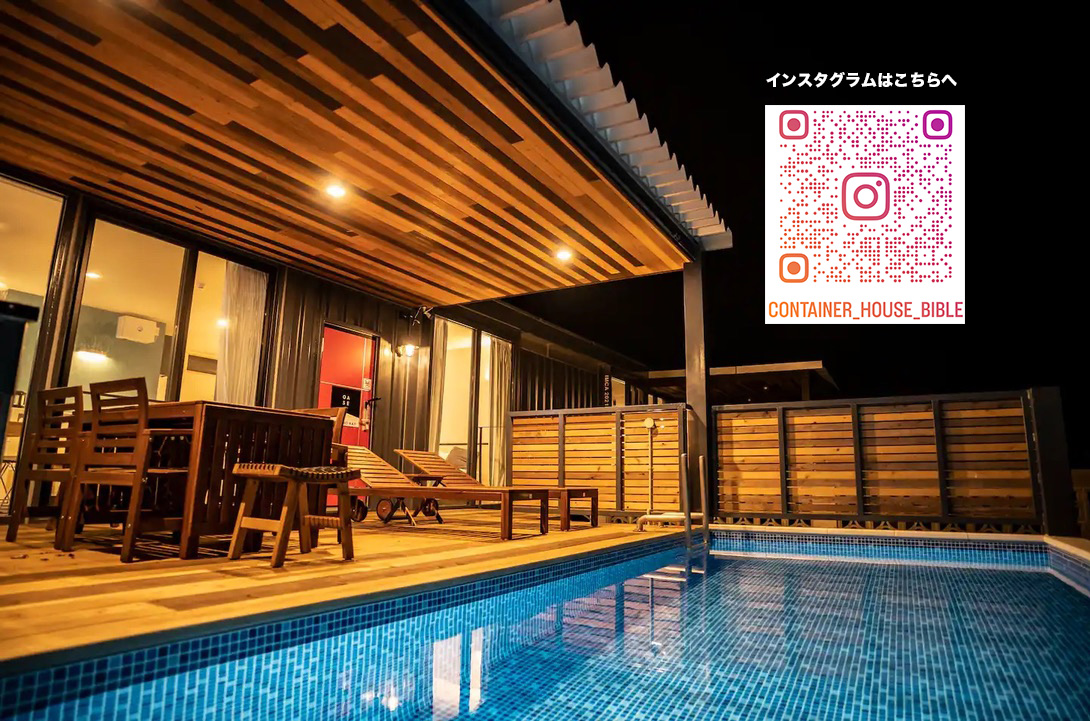シニフィアンとシニフィエの事について以前書きました。その事を理解すると、随分世界が見えてくるような話を書きましたが、今日の話題はそれに深く根ざしながら、とっても具体的な考え方を紹介します。当社では一つの指標(モノサシ)として考えるよりどころです。特に商業施設を計画する場合に使います。商業施設の計画は「好き嫌い」ではなく、「到達すべき着地点」があるからです。
建築を計画するとき、はっきりと認識したほうが計画がやりやすいと思われる概念があります。日常的に使われる言葉になっていますが「ライフスタイル」という言葉と、建築やインテリアなどのデザインのテイストやスタイルの関係性を考える概念です。この二つの概念を結びつける考え方をここで考えます。 「ライフスタイル」という言葉そのものが示しているように、人にはそれぞれの「文化」があって日々の生活の中での行動にある種の「スタイル」が現れます。世間ではよく「趣味」という言い方で表されたりします。この「趣味」というのは、基本的には普段は自分の事を考えていれば済むので、あまり人との差異を考えることはないのですが、人と話すととたんに解るように、結構大きな開きがあります。
人の趣味や宗教に口出しする気はありませんが、例えば仕事として「アパレル」をやっていこうという考えがあるのなら、お客様となる生活者はもちろん、それよりもまず自分の事をよく知って、自分が創り出していく自分の趣味の「オーダー(ありかた)」の方向性について明確な認識を持つことが必要になります。 下の表は「プテスティッジ性」-「ローコスト性」;「こだわり性」ー「ノーマルさ」を軸として表現し、人のライフスタイルを当社なりにカテゴライズしてみました。生活者達のライフスタイルをある言葉を借りてカテゴライズしたわけです。たまたまその言葉でカテゴライズしているだけで、言葉を変えると区切り方も変わってくるでしょうし、人はある一定の人格だけで生きてるわけでもないので、完全に分けられるものでもありません。何となくそんな方向性をもっているなあ。という感じでしょう。
それでも、下の表のようなものを作るとそれはそれで人が結構見えてくるものです。 占い師になろうというわけではないですから、こんな事をいつも考えながら生きていく必要はありません。ただ、あなたが自分の建築を計画する段階で、自分の立ち位置と、人々との相関関係を知りつつ計画していくことによって事業的戦略がとても立てやすくなるのです。ショップを事業的に立ち上げるということは、自分の趣味に合うお客様だけに来て欲しいという願いは解りますが、それだけではなかなか経営的に成り立ちません。だからといって、「どなたでもどうぞ」という造りでは基本的に「ブランディング」という作り出すべきイメージが作れません。結果的には誰も興味を持たない空間になるのが実体です。ある照準を中心に、ボリュームゾーンを排除しない形で明確なスタイルを打ち出すということになるのが経営的には正解ですが難しいことではあります。
ライフスタイルとデザインのスタイルをシンクロさせて計画する事を勧めているのですが、おわかりでしょうか?そのためにいろいろなライフスタイルについてある表現を試みました。これらの人々が好むデザインの傾向を知ることによって事業は格段に進めやすくなります。
※「マッピングメソッド」という呼び方も、「各カテゴリー名称」もarchimetal.jpがつけたオリジナル名称ですので、日本全国で通じる言い方ではありませんので念のため。

●cheap stage チープステージ:貧乏ステージというわけではありません。例えば100円ショップのモノを見て歩くとなんだか「えっ!これがひゃくえん?」と思うようなそういったバリュー感覚に価値を見いだすライフスタイル。ただし添加物だとか材料の履歴などそんな事は関係ない。「やすいがイチバン」のライフスタイル。
●retro stage レトロステージ:いつの間にか、遠い彼方のヒトになっていてもぜーんぜん気にならない。ある意味世捨て人。新しいものの感性や、流れなど気にならないし、それらの評価基準さえもない。おーい!どこにいるの?って感じの生き方。もちろん別に悪い訳じゃない。でも新しいものにいいものもいっぱいあるよっていっても耳貸さないですね。
●normal stage ノーマルステージ:なんというか、「フツー」の人。フツーの生き方。フツーの感性。でも「中庸」とは全く違う種類。特段変なわけじゃないが、フツー以外の事はこの方には別の世界に見えるので興味を示さない。
●populer stage ポピュラーステージ:ノーマルステージのライフスタイルに、「これはなかなかいいね」感覚が備わったライフスタイルパターン。こちらのほうがコトバとしては「普通」感覚で、フツーとはちょっと違う。ある程度「群」から離れようかなあという意識があるライフスタイルで、そのチェック意識も存在する。
●simple stage シンプルステージ:シンプルイズベスト感覚。余計なものをまとうことをいやがるライフスタイル。ちょっと昔の「無印良品」的ライフスタイルといえるでしょう。最近でいうとユニクロの方が近いかも知れない。
●casual stage カジュアルステージ:「軽いノリ」が好き。フォーマルな感覚って分からない。っていうか~、イヤ。大体そんな中身でもないくせになによすましちゃってさ、カジュアルが一番よ。だって身軽、走れる、飛べる、はねられる。そんな自由さが私に似合ってるのだぴょ~ん。って感じの明るい方々です。
●social stage ソーシャルステージ:人との関係の中で中庸を選ぶ生き方のことの名称として使いました。基本的に社交好き。だから出来れば人とぶつかることは避けたい。そんな私が選ぶのは決して目立つこともなく、でも「違いが分かる利口さ」を合わせ持った生き方。そんな私は社交好き。どんな話題にでもついていける気がする・・・気がする。気がしてるだけ・・・。
●authentic stage オーセンティックステージ:何でも鵜呑みにすることはない賢さを持ち、自分の価値基準を持って生きていく。誰かに何かを問われれば自分の意見が言える。それも受け売りではなく消化された自分の意見。そんな私は食べるものにもうるさいの。でもグルメ道をいく訳じゃない。そんな人間の欲望のコントロールができなくてどうするの?という生き方のことです。
●traditional stage トラディショナルステージ:「時の洗礼のチカラ」を最も信じる生き方。伝統的なものは生き残ってきたすばらしいもの。その歴史の長さがそのものの良さを証明しているじゃないか・・・。その歴史の延長線が好き、その学校の歴史、そのスポーツの伝統、先輩と後輩の関係。そんな事を守りながら生きていくことがとても大切だというライフスタイル。
●eccentric stage エキセントリックステージ:風変わりな事が自分にとって大事な生き方。人と同じはイヤよ。何か違うことをして目立つのもいいわ。正統派の中で群れているなんてとてもじゃないけど出来ないわ。って感じです。アイデンティティーの成立のためにあえて「人と違った道を選ぶ」そんなライフスタイル。
●artistic stage アーティスティックステージ:「芸術家的生き方」を旨とする。まあどういうことかよく分かりませんが、世間の経済システムだとか、社会的関係だとかそんなのは自分の興味の範疇ではない。私は口の中がこのクープで切れてしまいそうな、そり立ったクープのバゲットだけが好き。他のパンはパンじゃないよ。だって昨日は満月だったし、僕の気持ちは荒れているのさ・・・(嘘)なんかそんな感じの芸術肌とでも申しましょう。
●attack stage そうさ、これがパンなんだ。こっちはパンじゃない!!一体何を考えてるんだ。こんなパン投げ捨ててやる。それに比べてこのパンのなんと愛おしいこと。いったいどうやってつくっているんだろう。なっ何をするんだ!このパンをそんな皿に置いちゃだめだ!。てな感じが一時が万事、生活全般にわたる。それが一貫してればいいのですが、そうやって騒ぐ事が好き、だからいうことが日々違う。でも本人はそういうつもりじゃない。本当にその時はそう思っているのです。
●executive stage エグゼクティブステージ:多くの経験をし、知識を持った中で「私はこう思う」という経験則と知恵から発する類い希な説得力を持ち、決して奢らず、回りの者もその人を自然に信じている。でもちょっとだけ鼻につくその雰囲気・・・やはり自分に相当惚れてるタイプの方々なのです。
●broadband stage ブロードバンドステージ:私としてははじめて使う新ジャンル名。エグゼクティブステージの進化型と解釈される。時代の変化を読みとり、ものによっては「これで充分」「これでなきゃだめ」の使い分けがきわめて高偏差値的。ブランド品はイヤじゃなく、結構信じているけど、そうでないものの中から光るものを見つける努力もし、見抜くチカラも持っている。生きる基準の指標が柔軟で幅を持ちダイナミックレンジが大きい。
そんな訳で本日のお話は終了。最後まで読んだのはあなただけでした。